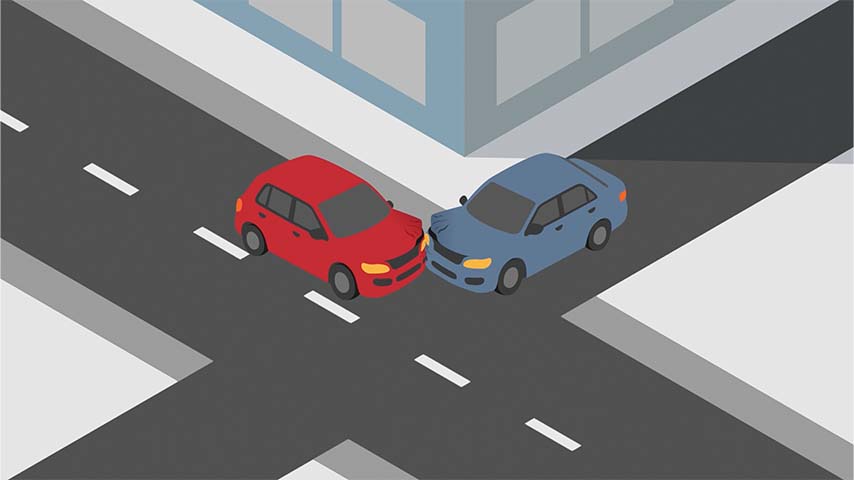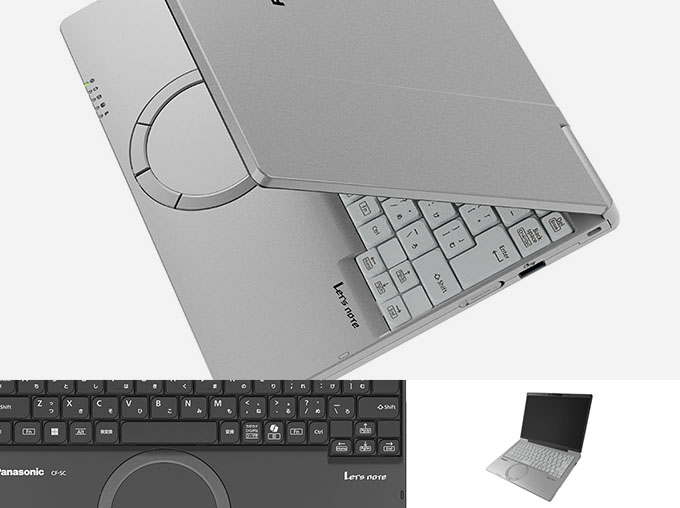企業が製品やサービスを魅力的に伝えるために、動画は欠かせない手段になっています。
しかし、いざ制作しようとすると「実写で撮影するか」「CGで制作するか」という選択肢に直面します。
どちらもメリット・デメリットがありますが、特に製造業やBtoB分野では、制作方法の違いが納期やコスト、表現力に大きく影響します。
実写撮影の特徴と課題
実写撮影は、現物の質感や動き、人物の表情などをリアルに伝えられるのが最大の魅力です。
例えば、手で製品を操作するシーンや、人物が説明する場面は、視聴者に安心感や信頼感を与えやすくなります。
しかし、その一方で課題も多く存在します。
- 関係部署や現場への撮影許可
工場や研究所など、撮影場所が限られている場合は、関係部署への事前連絡や承認が必要です。
セキュリティや安全面の配慮から、撮影日程の調整だけでも時間がかかることがあります。 - 撮影準備の手間
撮影機材や照明の搬入、現場のレイアウト変更、製品の設置・調整など、事前準備に多くの工数が発生します。 - 日程調整の難しさ
担当者や出演者、現場の稼働状況など、複数のスケジュールを合わせる必要があります。
そのため、撮影開始までに数週間〜数ヶ月かかるケースも珍しくありません。 - 再撮影のリスク
撮影後に仕様変更や修正要望が出た場合、再度撮影が必要になることがあります。
これにより納期やコストが大幅に膨らむ可能性があります。
CG制作の特徴とメリット
一方、CG(コンピューターグラフィックス)を使った制作は、これらの課題を大幅に軽減できます。
- すぐに制作開始できる
現物や完成品がなくても、図面や写真、仕様書があれば制作が始められます。
これにより、製品がまだ試作段階でも動画制作が可能です。 - 関係部署への撮影調整不要
撮影現場や人員を確保する必要がないため、社内調整の時間が不要になります。
特に大規模工場や研究所など、撮影許可に時間がかかる環境では大きなメリットです。 - 短納期での対応が可能
撮影日程に縛られないため、最短数日〜数週間での納品も可能です。
展示会や商談など、急なプロモーションにも間に合います。 - 修正が容易で何度でも可能
CGデータ上で形状や色、動きを変更できるため、撮り直しは不要です。
「仕様変更が多い製品」や「複数パターンの映像が必要なケース」に特に有効です。 - 見せたい部分だけを強調できる
実物では見えない内部構造や製品の動き、断面図なども自由に再現できます。
特許に関わる部分や微細な構造も、安全に分かりやすく表現できます。
実例:
実写とCGの使い分け方
実写とCGには、それぞれ得意な表現領域があります。
- 実写向き
人物インタビュー、使用シーンの雰囲気、リアルな質感や現場感を重視する映像 - CG向き
内部構造や動きの可視化、製品の未完成段階でのPR、短納期や多修正が必要な案件
特に製造業やBtoB製品では、複雑な構造や専門的な機能説明が必要なため、CGを選ぶケースが増えています。
例えば、展示会や営業資料用の動画では「限られた時間で製品の魅力を端的に伝える」ことが求められますが、CGなら見せたい部分をクローズアップし、余計な要素を省いた映像が作れます。
まとめ
実写は「リアル感」、CGは「自由度」と「スピード」に優れています。
現場調整や撮影準備の負担を減らし、短期間で高品質な動画を作るなら、CGは非常に有効な選択肢です。
特に「撮影が難しい」「社内調整に時間をかけられない」「修正対応を柔軟にしたい」という場合は、迷わずCG制作を検討すべきでしょう。
動画は一度作れば営業・展示会・Web・SNSなど、あらゆる場面で活用できます。
制作のハードルを下げ、スピードと効果を両立させるために、ぜひ実写だけでなくCGという選択肢も視野に入れてみてください。